noteに書いたものの転載です。(元になった文章はブクログに書いたものですが)
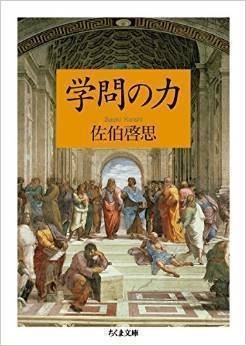
語り下ろしだけあって若干適当なポストモダン総括が飛ばしすぎてて楽しかったです。ニューサイエンスとポストモダン運動の混同とかね。
佐伯啓思ファンにはとてもいい本だと思います。回想や自分の学生時代の話、その時代の雰囲気がかなりの紙幅を以って語られているので。歌謡曲の話題が結構多いです。学徒・佐伯啓思を通した時代イメージは、ファンとしてはそれ自体興味深い読み物でした。
色々感想を書いていたのですが、メモをとりながら読んだ都合上、かなり細かな批判や異論が中心です(賛意などメモするに足りない。それは思考の産物ではないから)。とはいえ、本全体の雰囲気は伝わるのではないでしょうか。最後にも述べていますが、本書の白眉は五章であり、そこにバーキアンとしての、保守本流としての佐伯啓思の魅力が凝縮されていると思います。
本来保守とは、体制に対し、執拗に過去を想起し続けることで、懐疑的な視点を持っているはずです。急な変化に最も懐疑的な存在こそ、保守であるはずです。最近の保守はちょっと頭のネジが途方もなく外れているように思えてなりません。(余談はこれくらいにしましょう)
1、ネーションに対するナイーブさ
佐伯さんの思想で一番自己論駁的なのは、国(ネーション)という枠組みを無批判的に前提としているところです。ネーションステイト、まさに西洋的な出自の概念(ウェストファリア条約に、絶対王政下の臣民意識、何を思い出しても構わないですが)です。しかも、極めて近代的な概念です。近代や西洋特殊について、目ざとく出自を問い、その正当性を疑うのが佐伯啓思です。しかし、これについてだけは、佐伯さんが問題としているところを見たことがありません。これを説得的に展開できない限り、佐伯さんの主張は無内容なものになるのではないでしょうか。例えば伝統に棹さした「価値観」なるものが前提にしているのも、結局安っぽい経済保守の「国」イメージと何ら異なるところではありません。
2、サヨク批判ロジック――学校教育モデルによる批判の自己論駁性
戦後民主主義を、クラスにおける教師(こいつが解答を持っている)と生徒に例えている箇所があります(例えているというよりは、相似的に見ているのですが)。先生の答えを聡くも気付いて、うまく振る舞った「いい子ちゃん」がクラスのリーダー的になっていく、と語られています。もちろん、批判的に。だから、学校教育にも戦後民主主義にも、欺瞞を感じるのだ、と。
そのすぐあとでは、基本的人権や生命尊重主義を否定するわけではないと断りながらも、それをゴールであり目的のように設定するのはおかしいと主張されています。もちろん、そうです(アホでなければ左翼だろうとそう考えていた/いるでしょう)。しかし、佐伯さんはその後で、それは出発点であって、そこから目指すべき価値や理想を、土着的な素材を使って形作っていくべきだという。そういうものがないから、ゴールのように勘違いしたからサヨクはだめなんだ、というわけです。
ここで、先のクラスのたとえを思い出してください。形作られた理想なるものを、教師が用意している「解答」に、それに向って日々を生きる私たちを、クラスにおいて教師との距離感のゲームに置かれる生徒たちに読み替えてみましょう。先の学校教育のモデルに、そっくりそのまま読み替えることができるのではないでしょうか。
日本における独特な「理想」なるものを、うまく読み取って、適切に振る舞うことのできた「優等生」と、そこからは疎外されざるを得ない「劣等生」「不良」「外れもの」。社会や国の目標として、明確なゴールを設定することを、このロジックで正当化することは無理筋だと思います。(ちなみにこの批判は、「過剰包摂」に対する批判と同型です)
クラスからあぶれた者に佐伯さんは共感を示しているのですが、自身の左翼批判ロジックによって佐伯さんの主張は論駁されることになるかと思います。他人を批判するために持ちだしたモデルによって、佐伯さん自身も打ち崩されるというわけです。主張や信条先行で、言葉を組み立てすぎてはいないでしょうか。土着的なもの/日本的なものを利用すべきだという立場には、一定の共感を寄せるのですが、、、
3、ラベリングの粗雑――四章の「リベラリズム」
四章における「リベラリズム」というラベリングもさすがにずっこけました。政治思想におけるリベラリズムと、市場競争を謳うような新自由主義、それから合理主義、リバタリアニズムなどを一緒くたにします。さすがに無理があるでしょう。
「近代主義」「科学的な合理主義」「合理的な主体」なるものを前提している思想を、リベラリズムと佐伯さんは呼ぶのですが、フランクフルト学派やダーウィンが思想に与えたインパクト(アメリカの政治思想や、プラグマティズム)をどのように捉えるというのでしょうか。大まかに言って20世紀以降の哲学は、「理性過信」「合理性がもたらす非合理性」に対する反省抜きには成り立たないものになっています。先生が置いた三つの前提をピュアに信じている思想家がどれだけいるというのでしょうか。
リベラリズムの無力として語られているのも、「他者の生き方を好まないまでも、少なくとも認める」態度を持つような市民を、社会の構成員として想定しているだけのことです。他者の生き方を破壊するようなテロ行為は、リベラリズムからは認められない。ただ、それだけのことです。
「個人の生き方の相互調整」という問題については、フィシュキンの著作などを当たればわかるように、十分リベラリズムの枠内でも対処可能です。
佐伯さんのリベラリズムに対する攻撃は、対象の曖昧さ/論法の粗雑さが見られます。
佐伯さんが文化圏ごとの超越性の議論を通じて語っている世界イメージは、完全にハンティントンの『文明の衝突』ですね。「文明圏」ごとに異なる超越性――文明の持っている「原理」だと思いねぇ――があるのだ、と。超越性モデルを通じて、文化圏を跨いだ感情移入が可能になる……というアイデアは面白いのですが。。。
他文化圏に属する国家の行動を、超越性モデルを通じて「理解」したところで、対立は収まるどころか、「それゆえに/かえって」許せなくなるのではないでしょうか。現実もそうでしょう。
宗教研究本、宗教に関する新書、特集した雑誌が売れるのは、超越性モデルを通じて他の文化圏を理解したいという気持ちの現われでしょう。佐伯さんの見通しは現実に実践されている。しかし、実践されておこっているのは、「あいつらの行動のロジックはわかった。だからますます許せなくなった/わからなくなった」ではないでしょうか。
4、残念な保守?
この本は五章が白眉です。しかし、ここを読むにつけて、五章にあるような正しく保守たる(つまり、正しくバーキアンな)佐伯さんはどこに行ってしまったのかと思う。新潮新書から出てる、つまんな時評では単なる自民党シンパになってしまっている。
過去を想起し、社会秩序の劇的な変化にブレーキをかける。流れを重視して、耳にいいことを言う体制には常に懐疑の視線を送る。……五章に特徴的な保守本流の佐伯啓思は、単なるウヨになってしまったのでしょうか。新潮新書の残念なシリーズは、佐伯さんの気の迷いだったらよいなと思うのですが。
批判が多かったですが、佐伯啓思入門としても秀逸ではないでしょうか。おすすめです。オタク的知識と学問的知識の違いについて語っている箇所なども興味深く読みました。
今回は途中から、ここでメモを取りながら読んでいました。
今回もいい読書でした。
佐伯啓思『学問の力』(ちくま文庫)

